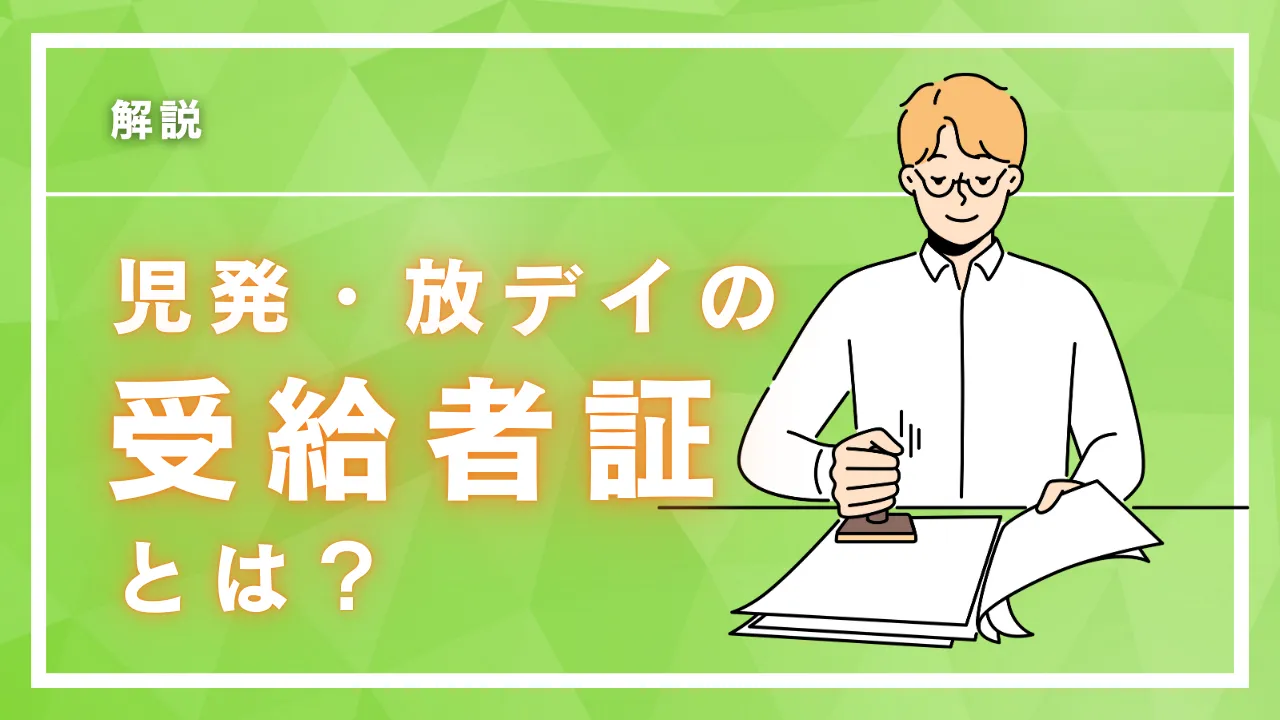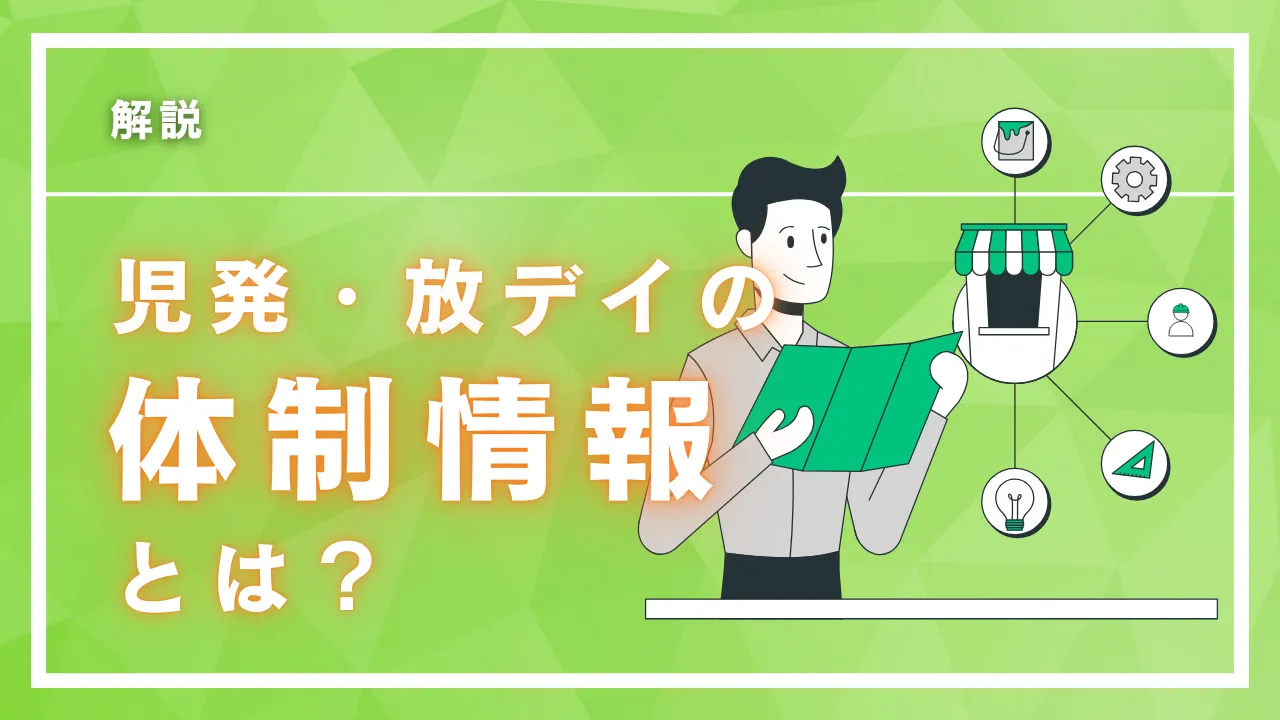児童発達支援と放課後等デイサービスは、発達に支援を必要とするお子様や障害のあるお子様にとって、その成長と発達を支える上で非常に重要な役割を担っています。これらのサービスは、お子様一人ひとりのニーズに合わせた療育や居場所を提供し、保護者の方々にとっても大きな支えとなっています。
この記事では、児童発達支援と放課後等デイサービスにおける「加算項目」について、保護者の方々をはじめとする非専門家の方々にもわかりやすく解説していきます。「加算項目」とは、基本となるサービスに加えて、さらに質の高い支援や特別な配慮を行う場合に、事業所に支払われる追加の給付金のことです。これらの加算金は、事業者がより専門的な知識や技術を持つ人材を配置したり、特別なプログラムを提供したりすることを奨励するために設けられています。
加算項目を理解することは、お子様がどのような支援を受けているのか、そして今後どのような支援が期待できるのかを知る上で非常に大切です。この記事を通じて、加算の仕組みや種類、その背景にある考え方を理解していただくことで、お子様の支援についてより深く考え、サービス事業者とのより良い連携に繋げていただければ幸いです。
目次
加算制度の基本的な考え方
加算制度の根底にあるのは、厚生労働省が定める「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」です。この基準は、障害のあるお子様への支援の質を向上させることを目的としており、加算はそのための重要な手段の一つと位置づけられています。政府の方針としても、放課後等デイサービスの質を高めるための加算を充実させる方向性が示されています。
加算項目は、サービスの質と個別支援の充実という二つの側面から、事業者の取り組みを後押しするものです。特定のニーズを持つお子様(例えば、重度の行動障害のあるお子様や医療的ケアが必要なお子様)への支援を強化したり、専門性の高い職員(例えば、専門的な研修を修了した職員や経験豊富な職員)の配置を促したりします。また、ご家族や学校、その他の関係機関との連携を推進することも、加算の重要な目的の一つです。このように、加算制度は、お子様一人ひとりの状況に応じた、きめ細やかな支援を実現するための仕組みと言えるでしょう。
主な加算項目
加算項目は、お子様の特別なニーズへの支援、職員の専門性や配置、関係機関との連携、運営体制の充実など、多岐にわたる視点から分類することができます。ここでは、主な加算項目について、その目的、算定要件、単位数などを詳しく見ていきましょう。
強度行動障害児支援加算
重度の行動上の課題を持つお子様に対して、専門的な支援を提供し、行動の改善と安全確保を図ることを目的としています。2024年の制度改正により、行動障害の程度に応じて異なるレベルが設けられました。
要件
専門的な研修(実践研修または中核的人材研修)を修了した職員の配置、支援計画の作成、自治体によるお子様の行動障害の程度の認定(放課後等デイサービスIIの場合はより厳格な基準)が必要です。
単位数
放課後等デイサービスI(児基準20点以上)で200単位/日、放課後等デイサービスII(児基準30点以上)で250単位/日、児童発達支援で200単位/日です。2024年4月1日以降の新たな算定開始から90日以内は、さらに500単位/日が加算されます。
ポイント
2024年の改正で、より専門的な支援の必要性が高まっていることがわかります。最初の90日間の単位数増加は、新しい支援体制の導入を促進するための措置と考えられます。
児童指導員等加配加算
基準となる職員配置に加えて、さらに多くの児童指導員やその他の職員を配置することで、お子様への支援体制を充実させることを目的としています。2024年の改正では、雇用形態(常勤・非常勤)や経験年数に応じた評価が導入されました。
要件
基準人員に加えて、常勤換算で1名以上の職員を配置する必要があります。追加配置する職員の資格や経験(児童指導員、理学療法士など)によって単位数が異なります。
単位数
定員10名以下の事業所の場合、職員の資格や経験に応じて90単位~187単位/日など、細かく設定されています。
ポイント
2024年の改正で、職員の経験や貢献度をより重視するようになったと言えるでしょう。保育士資格取得後の児童福祉事業における実務経験も評価対象に含まれるようになりました。
専門的支援加算 / 専門的支援体制加算 & 専門的支援実施加算
専門的支援加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士などの専門職による、専門性の高い個別支援を促進することを目的としています。2024年の改正で、体制加算(専門職の配置)と実施加算(計画に基づいた支援の提供)の二段階評価となりました。
要件
- 体制加算:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、経験のある保育士または児童指導員などの専門職を常勤換算で1名以上配置する必要があります。
- 実施加算:個別支援計画に基づき、専門職が専門的支援実施計画を作成し、それに基づいて30分以上の専門的な支援を行う必要があります。月間の算定回数には上限があります。
単位数
- 体制加算:定員10名以下の事業所で123単位/日など
- 実施加算:150単位/日、ただし月間の上限回数あり
ポイント
2024年の改正により、専門職の配置だけでなく、実際に専門的な支援が提供されることがより重視されるようになりました。月間の利用日数に応じた上限回数がある点に注意が必要です。
家庭連携加算 / 家族支援加算
ご家族との連携を強化し、家庭におけるお子様の支援をサポートすることを目的としています。2024年の改正で、家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合され、家族支援加算として、兄弟姉妹への支援やオンラインでの相談も評価されるようになりました。
要件
事前に保護者の同意を得て、個別支援計画に基づいた相談援助を行う必要があります。訪問や相談の記録が必要です。
単位数
支援の内容や時間によって異なり、以下のように設定されています
- 居宅訪問(1時間未満):187単位
- 居宅訪問(1時間以上):280単位
- 事業所内での相談、オンラインでの相談:別途設定
ポイント
2024年の改正で、家族支援の重要性が再認識され、より多様な支援方法が評価されるようになったと言えるでしょう。兄弟姉妹への支援も明確化された点は、ご家族にとって心強い変更です。
関係機関連携加算
事業所と学校、保育所、児童相談所などの関係機関との連携を強化し、お子様にとってより良い支援環境を整備することを目的としています。2024年の改正では、医療機関や児童相談所との連携も対象となり、個別支援計画作成時以外での情報連携も評価されるようになりました。
要件
事前に保護者の同意を得て、関係機関との会議の開催や情報共有、連絡調整などを行う必要があります。連携の内容に応じて、I~IVの区分があります。
単位数
連携の内容に応じて1回あたり150単位~250単位で、月に1回を上限とする場合が多いです。就職支援に関する連携は1回のみ算定可能です。
ポイント
2024年の改正で、より幅広い関係機関との連携が促進されるようになり、お子様を取り巻く様々な環境を考慮した支援が期待されます。
保育・教育等移行支援加算
放課後等デイサービスから保育所や学校などの教育・保育機関への移行を支援することを目的としています。2024年の改正では、移行に向けた取り組みや、移行後の家庭訪問、移行先との連携などが評価されます。
要件
保育施設等への移行に向けて、保護者や児童の状況を把握し、退所後30日以内の居宅訪問などを行う必要があります。病院や他の社会福祉施設、学校教育法第一条に規定する学校への入学の場合は対象外となることが多いです。
単位数
1回あたり500単位。
ポイント
この加算は、お子様がよりインクルーシブな環境へスムーズに移行できるよう支援することを目的としています。移行後のフォローアップも重視されています。
送迎加算
ご自宅や学校から事業所までの送迎サービスを提供することに対して支払われます。2024年の改正では、医療的ケアの必要性も考慮されるようになりました。
要件
車両による送迎が対象で、徒歩での送迎は基本的に対象外です。事前に保護者の同意を得て、送迎場所を定める必要があります。重症心身障害児や医療的ケアが必要なお子様の送迎には、追加の単位が加算されます。
単位数
片道あたり54単位が基本ですが、お子様の状態によって異なり、重症心身障害児の場合は94単位、医療的ケア児の場合はさらに高い単位数が設定されています。
ポイント
2024年の改正で、医療的ケアが必要なお子様への送迎に対する評価が向上し、より安全な送迎体制の構築が期待されます。
延長支援加算
通常のサービス提供時間を超えて、お子様の預かりニーズに対応した場合に評価されます。2024年の改正では、基本報酬の最長の時間区分を超えた支援に対して算定されるようになりました。
要件
事業所の営業時間が8時間以上であること(放課後等デイサービスの場合は平日3時間、学校休業日5時間以上)、事前の届け出、個別支援計画への記載が必要です。延長時間帯には2名以上の職員配置が求められます。
単位数
延長時間や、重症心身障害児であるかどうかによって異なり、30分以上1時間未満で61単位/日~2時間以上で256単位/日など、細かく設定されています。
ポイント
2024年の改正で、より柔軟な預かりニーズへの対応が評価されるようになり、保護者の就労支援にも繋がることが期待されます。
欠席時対応加算
利用予定日に急病などで欠席されたお子様に対して、事業所が行う連絡調整や相談援助を評価するものです。
要件
欠席の連絡が利用予定日の2日前から当日までにあった場合で、利用者や保護者への連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録する必要があります。放課後等デイサービスでは、利用開始後30分以内の早退の場合も算定できることがあります。
単位数
1回あたり94単位で、月に4回までが上限です。
ポイント
この加算は、お子様が欠席した場合でも、事業所がご家族との連携を維持し、次回の利用に繋げるための取り組みを支援するものです。
利用者負担上限額管理加算
複数の障害福祉サービス事業所を利用しているお子様について、それぞれの事業所の利用者負担額を合算し、世帯ごとの負担上限額を超えないように管理する事業所に対して支払われます。この加算により、保護者の方が複数のサービスを利用する際の負担額を調整し、安心してサービスを利用できる環境を整備することを目的としています。2024年度の制度改正による変更はありません。
要件
利用者負担上限額管理を行う事業所が、他の事業所や自治体と連携し、利用者の負担額を適切に管理する必要があります。
単位数
管理する利用者の人数や、管理を行う事業所の種類によって単位数が異なります。詳細な単位数については、各自治体の情報を確認する必要があります。
その他の重要な加算項目
上記以外にも、事業所の専門性や提供するサービス内容に応じて、以下のような加算項目があります。
- 福祉専門職員配置等加算:社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ職員を配置している場合に評価されます。
- 医療連携体制加算:医療機関との連携体制を構築し、必要な医療的ケアを提供できる場合に評価されます。
- 食事提供加算:栄養バランスに配慮した食事を提供した場合に評価されます。
- 送迎加算(特別支援学校等):特別支援学校等への送迎を行った場合に、通常の送迎加算に加えて評価されます。
- 自立サポート加算:高校生に対して、卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価されます。
- 人工内耳装用児支援加算:人工内耳を装用しているお子様に対して、専門的な支援を行った場合に評価されます 。
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算:視覚、聴覚、または言語機能に重度の障害のあるお子様に対して、専門的な支援を行った場合に評価されます。
- 中核機能強化加算・事業所加算:地域における障害児支援の中核的な役割を担う事業所を評価するものです。
- 集中的支援加算:強度行動障害のあるお子様の状態が悪化した場合に、集中的な支援を行った場合に評価されます。
- 虐待防止措置未実施減算:虐待防止のための措置を適切に行っていない場合に減算されます。
- 業務継続計画未策定減算:感染症や災害発生時においてもサービスを継続するための計画を策定していない場合に減算されます。
- 情報公表未報告減算:運営に関する情報を適切に公表していない場合に減算されます。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算:福祉・介護職員等の処遇改善に取り組んでいる事業所に対して加算されます。2024年度の改正により、既存の処遇改善加算が一本化され、加算率が引き上げられました。
これらの加算項目は、それぞれ算定要件や単位数が細かく定められていますので、詳細については各自治体の資料や、利用している事業所にご確認ください。
まとめ
本記事では、2025年3月時点における児童発達支援・放課後等デイサービスの主な加算項目について解説しました。2024年度の制度改正により、加算の種類や算定要件が大きく見直されたものもあります。これらの情報を活用し、お子様がより質の高い、そしてそれぞれのニーズに合った支援を受けられるよう、保護者の皆様も積極的に関わっていくことが重要です。ご不明な点やさらに詳しい情報が必要な場合は、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口にご相談ください。